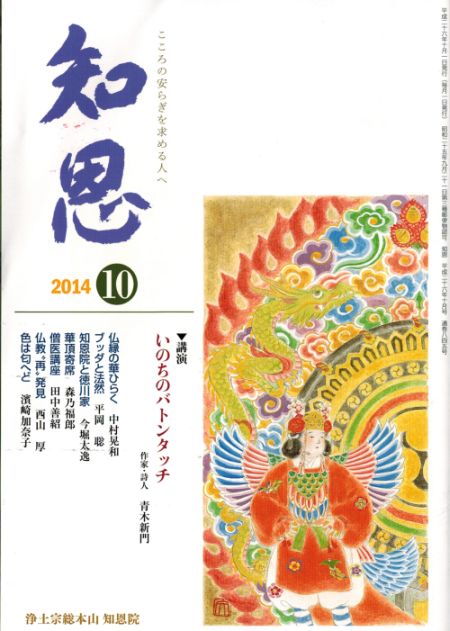フジノが雫有希選手をこころから応援する理由
何故フジノがこの2.14横須賀大会を応援しているか?
いくつかの理由があって書ききれないのですが、そのうちの1つを今日は記したいと思います。

フジノ事務所を訪れて下さった雫有希選手
フジノは長年のプロレスファンですが、雫選手のことを初めて知ったのは2010年10月の週刊プロレスという雑誌を通してでした。
世界で最も大きいWWEというプロレス団体を辞めて日本に帰ってきたTAJIRI選手が立ち上げた『SMASH』という団体がありました。
そこでは男子も女子も垣根を超えて試合が行なわれていました。
その女子のチャンピオンが華名選手というのですが、試合の相手に指名したのが当時の雫あき選手だったのです。
華名選手(プロレスだけでなく格闘技も強くフリーで活躍してきたかなりの人気選手)を追い詰めた上に、華名選手から賞賛の言葉まで引き出した雫選手は、明らかにシンデレラでした。

2010年、左・チャンピオンの華名選手、右・雫あき選手
この試合の評価は高く、今でもインターネットをちょっと検索すればプロレスファンの観戦記がたくさん出てきます(例えば、こちら)。
その後も、週刊プロレスにはたびたび取り上げられるなど、順調なプロレスラー人生を送っているのかと思っていました。
しかし、そんなことは無かったのです。
「知恩」に連載された雫選手の本音
雫選手と初めてお会いした日に、フジノに3冊の本を雫選手は渡してくれました。
浄土宗総本山知恩院が出版している月刊誌に『知恩』という本です。
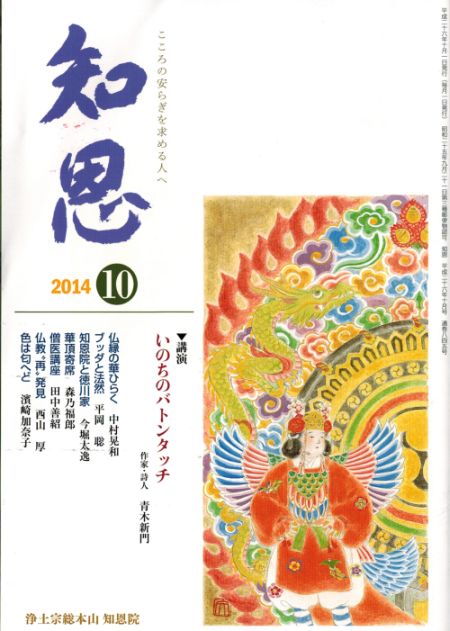
「知恩」2014年10月号
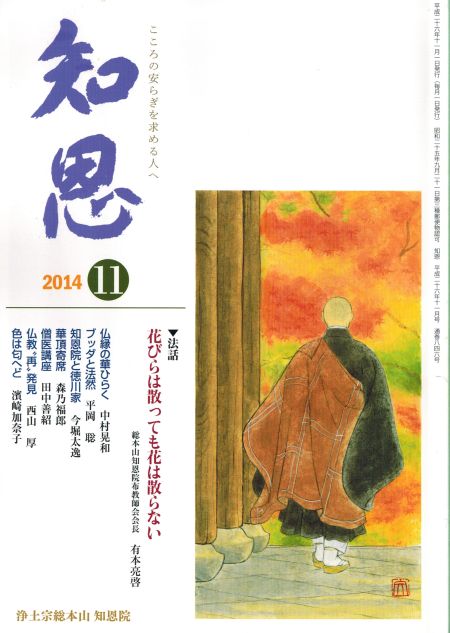
「知恩」2014年11月号
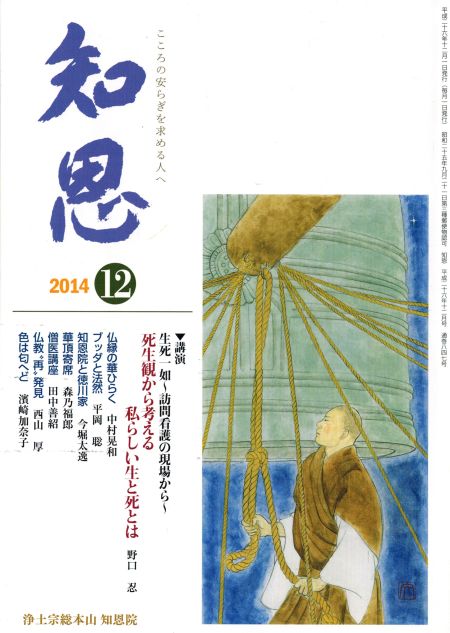
「知恩」2014年12月号
雫選手は、プロレスラーでありながら尼僧であるという存在です。そのような関係で、『知恩』に連載がなされたのです。
ここに、フジノが「これから雫あき選手は順風満帆だ」と思っていた頃のことが記されていました。
予想していたのとは全く逆の人生が描かれていました。
全文を引用します。
プロレスを通じ乳児院支援(1)
●乳児院支援で学んだこと
最初にお断りしておきます。
私は18歳まで在家で育ち、女子プロレスラーという職業を経て養成道場に入行し僧侶の資格を取らせていただきました。
宗門の大学だけでなく様々な分野に門戸を広げている浄土宗教師養成道場では、私のような存在は特別ではなく、会社員など異業種を経て様々な事情のもと僧侶になられ、今なお仕事を継続されている方と何ら変わりはありません。
決定的に違う要素といえば私がプロレスラーだということだと思います。
第一私ごときが尼僧なんて肩書きをいただくのもおこがましい気さえします。
髪の毛も仲ばし、化粧もおしゃれも好きで、プロレスだってやる。
俗世に浸かっている、ただの女性でしかないと考えています。
さて、私がプロレスを通じ2010年より普光寺大本願乳児院にプロレス興行の収益を寄付させていただくことによって学んだことは「人の役に立てる喜び」よりも「人間はいかに醜く、愚かで、しかしながら愛らしい」ということ、そして「一歩間違えれば自分が死ぬか相手が死ぬかの中で悟った死と命の重み」だと思います。
●無名から一躍スターに
私は、元々盛り上がりに欠けていた地域の縁日にプロレスを導入しただけの無名のプロレスラーでした。
いわば「名も無き路上のプロレスラー」の私が養成道場に入った2011年に、かつてアメリカで「プロレスのメジャーリーグ」と言えるWWEでスターだった選手のプロデュースするプロレス団体から
「君の活動は素晴らしい、ぜひうちのリングに上がってみないか?」
と誘われ、メジャー団体のリングに初めて上がったのです。
あの藤波辰爾、天龍源一郎の試合の後に組まれた私の試合。
「無名の逸材」という名のもと当時の女子王者との対戦が組まれました。
敗れたものの後楽園ホールにいた約1200人の観衆から「大・雫あき(当時のリングネームは雫あき)コール」がわき起こり、まさに底辺からメジャーに登った「リアルシンデレラストーリー」でした。
「誰からも好かれる崇高な選手」と専門誌の一面も飾りました。
●謙虚にしていてもパッシング
しかし、一方で「こんな時こそ謙虚に腰を低く」と、日ごろ思っていたことを貫いたにもかかわらず、今まで友人だった学生時代の知人は謙虚にすればするほど去って行ったのです。
そして同業者までも。
某巨大匿名掲示板掲示板には、あることないことが書き込まれ、プライベートのメールアドレス、家族の様子まで晒されるようになりました。
いつも人に好かれることばかりを考え、自分を押し殺し、笑顔でいた私は、ある日、目を見開いたまま意識を失い、家族に発見されるという事態にまで陥りました。
当時24歳の私には酷な話でした。
(次の記事に続きます)